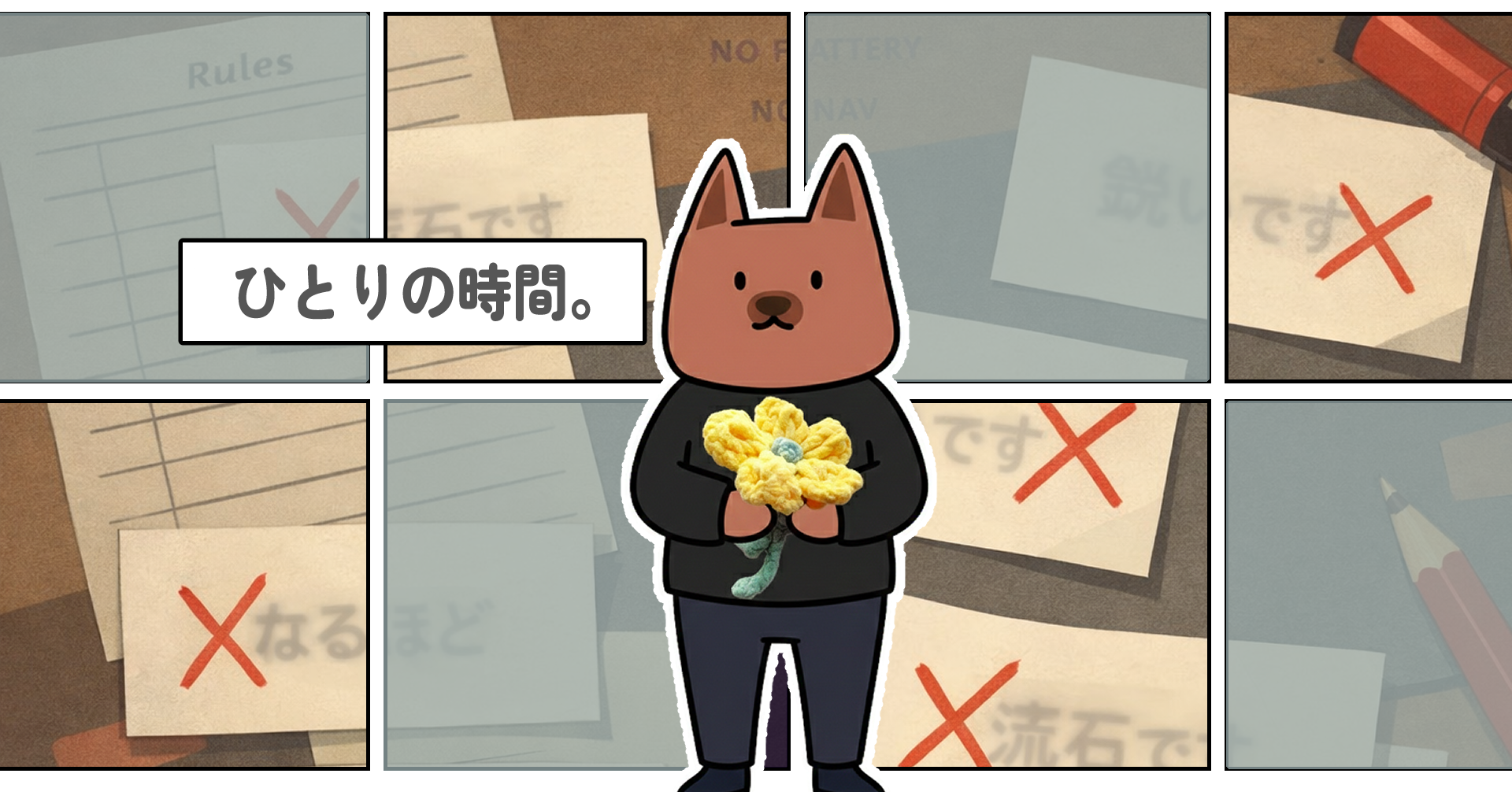【途切れた物語】07
辺りは常に暗く不気味な獣の鳴き声が聞こえる森だった。
今朝森に入ってからずっと聞こえる声は侵入者を警戒しているのか、それとも警告でもしているのかいつまでも止む気配が無い。日光を遮断してしまうほど生い茂った木々は鬱蒼としていて、木漏れ日すら落とさない木々の重なりはどこか圧迫感を感じる。
イメラとロイは黙々と森の中を歩いていた。舗装された道などなく、獣道をコンパスと地図を頼りに歩く。
「休憩だ」
「ええ」
昨日から会話も少なく、日ごろよく話すイメラはなにか考えているのか無表情のままだ。ロイもそんなイメラに茶々をいれる気はないようで無言に徹している。
頭上を見れば葉の天井がゆらゆらと揺れている。風が吹いているようだが、ここにはまったく届かずほぼ無風だ。漂うじめり気にイメラは無造作に髪を縛りあげる。首元に空気が触れ幾分涼しくなったことでイメラは小さく息を吐いた。ずっと歩き通しだったのだ。流れる汗を手で拭う。
視界に腕に絡む黒髪が見えた。用心のため髪色を魔法で変えたのだが、やはり長さも変えてしまおうかと思う。ロイが止めたため切らなかったのだが邪魔だ。
「イメラ」
「なに」
「お前は伝説を知っているか?勇者の」
「勇者?」
突然の話に面食らう。けれど思い当たるものがあった。
むかし争いの絶えない時代、1人の青年が立ち上がり何度も困難に立ち向かい、そして世界に平和をもたらしたという物語。城にいたときに絵本でよく見たものだ。自分以外にも誰かが何度も読み返しただろう跡がある古びた絵本だった。
その絵本に勇者の挿絵があったのだが、それよりも部屋に飾ってあった勇者の肖像画のほうがひどく印象的だった。勇者を見た画師がなんの飾りもせず見たそのままを描いたのだという勇者は、無表情で生気を感じられなかった。短い黒髪が顔にうっすらと影を作っていて、子供心に大丈夫なのかなと心配してしまうほどに生きている感じがしていなかった。
「ええ知っているけれど、どうかしたの?」
「勇者の話は実際に起きたことだそうだ。といっても本に残されているものに虚偽はあるだろうが、大筋は合っているらしい。勇者はただの人間だってよ」
「人間。そうよね……争いを起こしたのも人間よね」
「だな」
ロイが立ち上がる。休憩は終わりらしく、また歩き始めた。体も慣れてきたのか長距離でもそうへばったりはしない。歩き通しでよく足に肉刺もできたものだが、いまは厚くなった皮膚に怪我はない。けれどたまにグラリと頭が揺れるような感覚が襲ってくる。あの村を見たあとからだ。
イメラは少しだけ水を口に含ませ口内を潤す。ちゃぷんと鳴る水音が心地いい。
「なあ」
淡々とした声だった。足を止めないまま呼びかけてきたロイに、イメラは少し視線を落とす。
「勇者は勇者じゃないらしい」
「……どういうことかしら?」
「そのままだ。俺たちが呼ぶ勇者は自分のことを勇者ではないと言っていたらしい」
「じゃあ勇者は誰かが作ったものなのね」
誰かが勇者という形を作り、それに当てはまる誰かに名をつけた。勇者と呼ばれた誰かはそんな状況が辛かったんだろうか。ふと肖像画を思い出す。
そういえば勇者とは一体なんなのだろう。なにをもって勇者と言うのだろうか。
「勇者は悪を倒して世界を平和にしたが、それは勇者が本当に望でいたこととは違うらしい。……勇者は自分のことをただの人殺しだと言ったんだ。多くの人が望む結果に繋がっただけで自分がしていることは、したことはただの自己満足だってよ。旅で連れ立った子供を助けられず死なせてしまい、道中出会ったお姫様の願いは叶えられず、悪は救えず──勇者ってなんだろうな、って哂ってたそうだ」
何故だろう。
自分よりも大きな背丈、見慣れたロイの後姿が小さく見える。イメラは頬に伝う汗を拭う。声を出すのも憚られた。何故、そんな話を知っているのかなんて、言えなかった。
「印象的だったのが、勇者の姿を見て思い描く勇者とは違うと失望した奴らに、勇者が『俺はあなた方の悪魔にもなれるらしい』と言ったところだ」
ロイが止まる。後ろに一つで縛られた髪が大きく跳ねて動かなくなる。光に当たって茶色の髪が少し金髪に見える。ああ、きっと着いたのだろう。森の出口がすぐ近くに見えた。久しぶりの眩しい明かりに眼が眩む。
「ここから10分ほどで街に着く。……来るか?」
見下ろしてくる眼に、ほんの少し心が揺れる。しかしイメラは頷いた。
「せいぜい後悔しないことだ」
早足に歩くロイに慌ててついていく。辺りに気を配っているらしく、背中に緊張が走っている。なにをそんなに警戒しているのだろうか。ロイが言っていた通り、街はすぐ近くにあった。ラディアドル城下町にも劣らない発展した街だ。久しく見る賑わいにイメラは眼を見張る。市場を行き交う声に、色とりどりの品、響き渡る音楽、食欲をそそる香りに、立ち上る湯気、楽しそうに笑う人々、鎧に身を包み巡回する人、レンガで組み立てられた建物は見栄え良く飾られていてとても美しい。物も人も溢れる豊かな街だ。活気に満ちている。
それらを横目で窺っただけで忙しなく動くロイに少しの不満を持ちつつもイメラは後ろに続く。数秒眼を逸らそうものなら見失ってしまいそうな人混みだ。しかも、髪色が違えど絶世の美女に変わりないイメラを見た人々が我が眼疑い二度見しようと立ち止まるため普段より流れが悪い。
「ねえ、君」
「なにかしら?」
突然誰かに手を掴まれてイメラは振り返る。そこには痩せ身の長身の男がいた。どことなくランダーに似ている。
「この街初めて?よかったら案内するけど」
「嬉しいけれど遠慮するわ。つれがいるのよ。約束してるから」
でも、と言いかけた男の言葉を振り切ってイメラは視線を戻す。案の定ロイの姿が見えなくなった。路地に入ったところまでは見た。イメラは人の流れに逆らいながらようやく路地に曲がる。不思議なもので路地に入ると人の姿がぐっと減り、音が遠ざかる。どことなく温度まで下がったような気までしてくる。影の差す路地裏にはロイの姿が見えない。
イメラはゆっくり歩き出す。壁にもたれしゃがむ老人を通り過ぎる。暗いとは違う。静かだった。目の前を、先ほど見た人々とは違いボロを着る少年たちが楽しそうに追いかけっこをして通り抜けていく。笑い声が静かな空間に木霊した。
「あ」
ロイが魔法を使った。
イメラは肌に伝わる振動に気づき、魔力を感じる場所に足を進める。共に過ごす時間が多いからか、自然とロイの魔力が分かるようになった。魔法を使ってくれさえすればどこにいるか大体把握できる。そのせいでディバルンバでは迎えにこさせられたり使われたりもしたがちゃんとした使い道もあったらしい。
「──これが今回の分だ」
ロイの声が聞こえた。
けれど呼びかけるのは憚られて、足まで動かなくなる。分かっていたのだ。なんとなく、そんな気はしていた。
「ふん。ならこんなもんだろ。……ああ、前みたいな女はいねえのか?アレはなかなかよかった。どうもいいとこのもんらしくって需要が多い」
「いないな」
「まあいい。次も頼むぜ」
誰かが去る音が聞こえた。重いものを引きずるような音だ。足を引きずっているのだろうか。イメラは壁にもたれながら足元を見つめる。人に踏まれ出来た道の端に隠れるようにしてひっそりと花が咲いている。
「用は済んだ。帰るぞ」
「……ええ」
角から姿を現したロイを見上げ、イメラは微笑む。情けなく下がった眉を見てもロイは表情一つ変えない。
路地裏を出ると、世界が色を取り戻したように熱や音、光が戻った。けれどイメラはなにを見る気にもなれなかった。自分を見てくる視線も、途中先ほどの男のように声をかけてくる男たちにも元気よく営業をかけてくる快活な声も、どこか壁を挟んだ世界のように目に映る。
──ああ。きっと、これがロイたちがしてたことなんだろう。
街を出て、まっすぐ森に向かうロイの背中を追いながら悟る。
初めて会ったあのとき、ロイたちはきっと私のことを商品として見ていたのだろうと実感はしなかったが予測は出来ていた。けれど私には圧倒的な力があるから、だからこそそんなロイたちに興味を覚えてロイたちを通じて世界を見たいと思えた。そしてロイたちと過ごしていかにロイたちがあの村を大事にしているのかが分かった。
きっとそうだろう。ロイたちはあの村を存続させるため、守るため、あの村人たち以外を襲ってお金にしている。さっきロイと話していた奴が言っていた前みたいな女というのは、きっと、ロイたちが襲ったあと売った女ということだろう。
森に入り、すうっと影が差す。
──でも何故、ロイはわざわざ魔法を使ってまでして私が取引現場に来れるよう道案内したんだろう。
ちらりと様子を窺うが、ロイは背中を向けたままでペースを落とさない。辛い、わね。ここ数日、まともに話せていない。それがどうも一番辛い。頭の整理はつくのに、感情がうまく追いつかないのだ。
「……あら?湖?」
気がそれていたせいか、すぐ隣にきてようやく湖の存在に気がついた。見渡してみればこの場所だけ天井を覆う木木がなく、光が差している。光に反射する湖は透明度が高く、輝いていた。森に囲われているその光景はどこか守られているようにも思う。神秘的な場所だ。
「綺麗な場所だわ」
「そうだな」
「って、え?あれは、遺跡?見てロイ!湖の中に遺跡があるわ!」
「湖の中には入るなよ」
「え!?ば、馬鹿ね。入らないわよ」
「どうだか」
クッ、とロイが笑う。
目を見開くイメラは一瞬困ったように視線を逸らしたあと、ほんのりと頬を赤くしながら拳を作る。
「馬鹿にしてるわね」
「さあな」
「あ」
「なんだ」
ロイの背後にそれはあった。湖を眺める特等席とばかりに、森の合間に半円を描いてある空間に小さな白い花が所狭しと咲いている。見覚えのある花だ。そういえば城を出たときにも見た。名前は、なんと言っただろうか。昔教えてもらったはずなのに思い出せない。
「あの花の名前って、なんだったかしら」
「……ああ、あれか。ラシュラルだ」
「ラシュラル」
「行くぞ」
「え、ええ」
手を引かれて戸惑いを覚えながらもイメラは振り返ってラシュラルの花を見る。そうだ、昔、母に教えてもらったのだった。庭一面に敷き詰められた白い小さな花。
「掴まってろよ」
手を力強く握られてはっとする。一瞬ぐにゃりと曲がった視界が森でもなく湖でもなく真っ暗な空間になる。眼が見えなくなったのかと思ったが、よくよく見ればどこかの家の中みたいだ。転移したのだろう。むっとした空気の中、うっすらと輪郭を持つ部屋は広いとはいえない。こんなに落ち着いていられるのは繋がれた手から伝わるロイの体温のお陰だろう。
ロイはイメラが落ち着いているのを確認した後、迷いを感じない足取りで進み、ドアを開ける。予想通り家だった。しかも見覚えのあるものだ。ディバルンバにある使われていない、少し村から離れた場所にある家だ。
手は繋がれたままだった。
……ふと、風に乗って笑い声が聞こえた。きっとこの声はリヒトくんにセリナちゃんにシーラちゃんだろう。もっと耳を澄ませば彼らに混じって大人たちの声も聞こえてきた。
ああ……
世界はなんて美しく、残酷なんだろう。
数ヶ月しかここに居なくても分かったロイたちの秘密をこの村の皆が知らない訳が無い。それをよしとするロイたち、なにも言えないまま甘んじる村の皆。
──俺はあなた方の悪魔にもなれるらしい。
思い出した言葉が頭に何度も響き渡る。
私は。
「ロイ」
「なんだ」
「教えてくれてありがとう」
「そうか」
「……今日は、鶏肉でも焼こうかしら」
「それは……楽しみだな」
ロイを見上げる。丘の上から村を見下ろしていたロイもイメラを見た。困ったように、泣きそうに、口を吊り上げて笑う。
「お前の作ったやつは、美味いんだ」
「当然よ」
歪んでいくロイの姿に眼を逸らす。ポツリと落ちた涙が地面にシミを作って、消えた。
創作小説の番外編など更新一覧
- 17.ラミア建国歴史【途切れた物語】017 昔、美しい女がいた。 華奢な身体に白い肌を持ち、腰ほどもある美しい金の髪を持っているそ
- 16.ラディアドル国【途切れた物語】016 「嘘よ、嘘よね……っ!」 イメラは反発してくる力に魔力をねじ込ませて、ディバルンバへ、
- 閑話06帰れる場所【途切れた物語】閑話06帰れる場所 ロイとイメラのお話 「驚いた。ランダーが言ってたこと、本当だったんだな」
- 15.理想と現実【途切れた物語】015 悪趣味に思えるほどの贅がつぎこまれた飾りや建物の造りを見渡してイメラは溜息を吐く。 「
- 14.明日を想う【途切れた物語】014 「イグリティアラ様ー!またここに来ていたんですねー!!あんなに1人で出歩かないでくださ